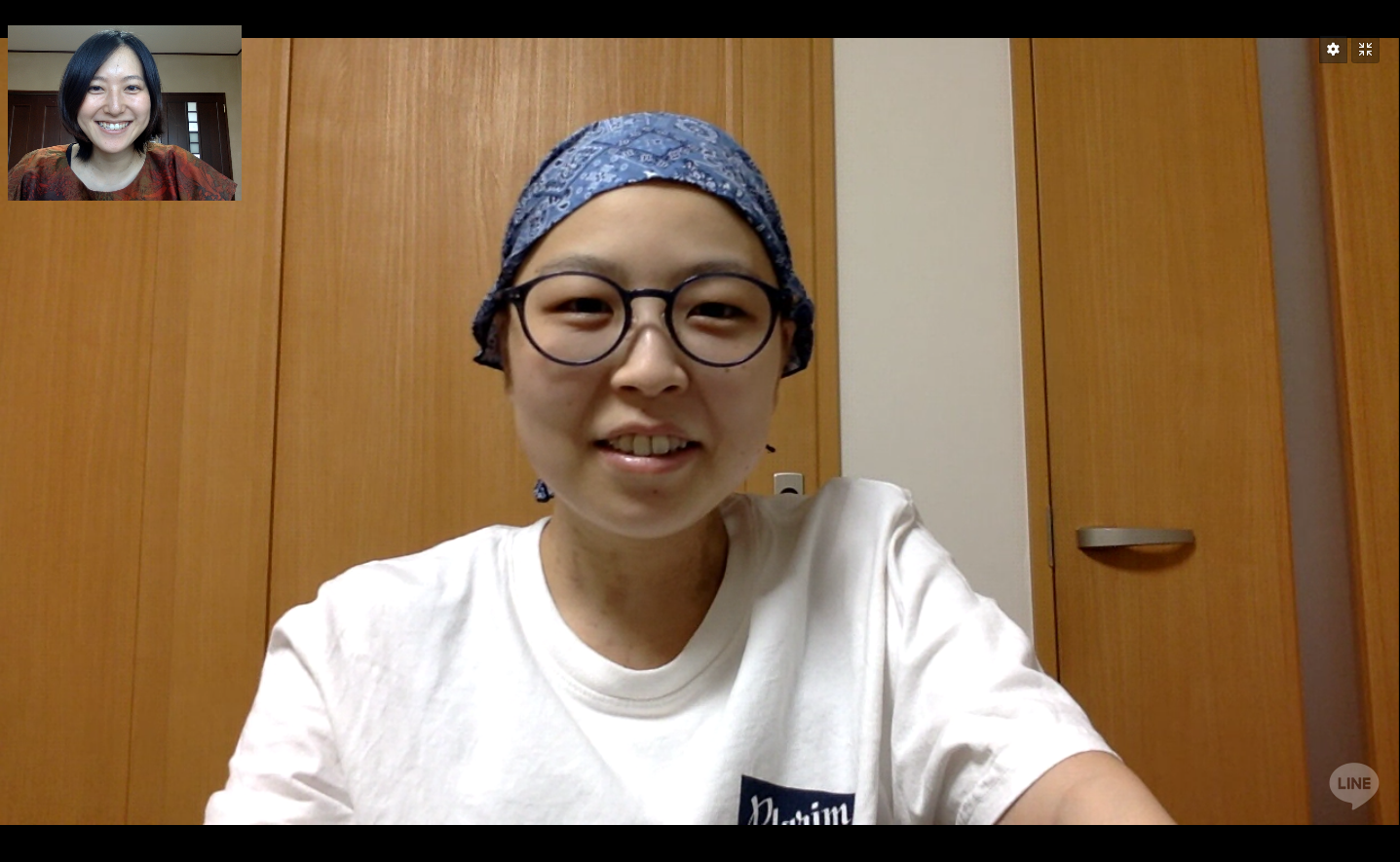シンガーソングライターとして活動する竹本健一さんは、ゴスペラーズ、CHEMISTRY、ジャニーズWESTなどにも楽曲提供している音楽家だ。自分の音楽が世界中で聞かれているって、どんな感覚なんだろう。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、大きな転機を迎えている音楽業界。その節目を竹本さんはどう捉えているのだろう。
竹本さんが見ている世界をちょっと覗きたくて、インタビューをお願いしたところ快諾してくださった。
歌っていること自体が楽しかった

シンガーソングライターとして活動されている竹本さんですが、小さい頃からずっと歌は好きだったんですか。
家の中で歌うことが好きでした。人よりうまいんじゃないかって思ってましたね(笑)
そういうのがないと、歌手になりたいとは思わないんじゃないでしょうか。「歌だけは負けたくない」って思って。小学生の時にみんなの前で歌を発表する機会があって、その記憶は鮮明にありますね。声が裏返って上手く歌えなかったんですけど。
両親が音楽をしていたわけではないので、音楽との出会いはテレビでした。
なるほど、出会い自体はそれほど特殊ではなかったんですね。
高校生になってからも、特に音楽をせずにハンドボールをやっていました。でも漠然と、「いつかは音楽をやりたい」って思ってたんですよ。
当時は音楽の”やりかた”もわからないし。というかただ部屋で歌ってるだけで、音楽作れないし、演奏できない。それなら、仲間を作ればいいと思ったんです。そこで、高校三年生の時に音楽大学を目指すことにしました。音大になら、音楽できる人たくさんいるはずじゃないですか(笑)
間違いないですが、高3になってから思い立つのがすごいな…。
そこで音楽の先生にお願いして、放課後に音大用受験のレッスンを受けました。初見の楽譜をパッと見せられて、それを歌う練習とか。ある日先生が音大の過去問を持ってきてくれたんですが、一問もわからないんですよね。まあ、音符も読めないし当然です(笑)
先生が「な?できへんやろ?」って言ってましたね。音大を狙うのは諦めました。
あ、やめたんですね!
音大はやめ、浪人して、大学へ行って、音楽サークルに入ることにしました。
僕の好きなブラックミュージックをアカペラサークルの先輩が歌っているのを聞いて、確かBoyz Ⅱ Menの「Thank You」だったと思いますが、それでそのサークルに入ることを決めて。
それからですね、人前で歌うようになったのは。
そこが初めての”ステージ”だったわけですね。
アカペラサークルにも、音楽の知識を持っている人がたくさんいたので、たくさんのことを学びました。例えば「ラ」っていう音にも高い低いがあること。それがいわゆる「ピッチ」と呼ばれるもので、ピッチが合わないとハモらないことなんかも。
そうなんだ!「ラ」って、「ラ」でしかないと思ってました…。
当時、まだ作詞作曲はされてなかったんでしょうか。
表立ってはしていませんでした。でも、自分の中から生まれてくる音楽はあったので、MDに録音したりはしていましたね。
そのときはずっと関西での活動ですか?
そうですね、生まれてから大学まで大阪でした。
大学でアカペラをやる傍ら、ほかの大学の人たちとバンドも組んでいました。「たけもん。」っていうバンドだったんですが、FLOWER FLOWERなどで活躍してるベーシストの真船勝博さんとか、今でもプロのミュージシャンとして活躍してるメンバーがいるんです。
そのバンドの女性メンバーが、東京の人と結婚することになりました。「結婚するまでの間、旦那は東京の新居で一人ぼっちだから、しばらく居候したら?」って言われて。今考えたらなんでそんな提案してくれたんだろうって思うんですけどね。
えっと…バント仲間の旦那さんと、東京でしばらく二人暮らしする、ってことですか?
はい。そう言われて、もともと旅行するタイプではないし、大阪から出たこともないから、「行ってみようかな」と思って。大学を卒業してすぐの6〜9月、東京で暮らしました。
旦那さんとは、1度しか会ったことなかったんですけどね(笑)
よく決断されましたね!!!
ね?(笑)
実はその旦那さんは日比野則彦さんっていう方で、すごいサックスプレイヤーだったんです。有名な音楽を作曲していました。ボストンにあるバークリー音楽大学という名門校を、首席で卒業するような人で。
でもなぜか新居にはクーラーがなくて、ものすごい暑い夏を過ごしたんですけど、でもあの3ヶ月があったから今があると思います。
東京に行くと決断されてよかったですね。
それまで、音楽で食べていくにはデモテープをレコード会社に送って、オーディションを受けて、認められたらデビューする、そんな道しか知らなかったんです。でも東京に来たら、レストランで演奏して稼いでいるミュージシャンもいるし、レコーディングやツアー回ってる人もいるし、作詞作曲に特化している人もいるし…音楽への携わり方は色々だなということに気づかされたんです。
東京にいた3ヶ月でいろんな人との出会いがありました。日比野さんが始めたバンドに僕も参加する流れになったのですが、それが3ピースバンド「PHONES」の前身となる活動でした。そして、その中の3人で「PHONES」を結成したんです。
渋谷や桜木町でストリートライブをやっていると、タワーレコードに出入りするレコード会社の社員さんたちが横を通って、僕たちを見つけてくれました。そうして、上京してから2年弱でデビューすることになります。
すごくスムーズに聞こえるんですが、もし結果が出なかったらどうしよう、なんて将来のことを色々想定されていたんですか?
いや、全然想定してないです。でも、日比野さんとの共同生活のあと、「PHONES」のドラマーと共同生活をし始めていたので、ある程度一緒にやっていくぞという覚悟はあったと思います。
めっちゃ一緒に住みますね(笑)
あはは。そうですね、あんまり一人で住むのが好きじゃないんですよね。

それでとんとん拍子にデビューが決まったというわけですね。
そうですね。曲を作って、歌えていること自体が楽しかった。他のバンドメンバーは年上だったから、運営は任せていた部分もあります。
そのメンバーで数年間活動されてたんですよね。
そうですね。2003〜2007年まで活動してました。ほんと忙しかったですね。レコード会社との契約では「アルバム○枚シングル○枚作ること」って決まっているんです。それをこなすのが大変でした。
多忙な5年間だったんですね。活動休止に至った経緯は?
バンドが上手くいってないなという実感と、ソロのシンガーとしてやりたいという想いからでした。所属しているレーベルも事務所もなくなったので、そのときから2015年あたりまではフリーランスに近い活動をしていました。
フリーランス・ミュージシャンとしてのスタートはスムーズでしたか?
スムーズとまではいかないけれど、苦しくはなかったです。ソロアーティストとしてのライブ活動に加え、作曲家としてコンペに曲を出したり、他のアーティストのライブにコーラスとして参加したりもしていました。
苦しくはなかったとは言え、売れていたわけではありません。ワンマンライブのチケットを売るために代官山でサンプルCDを配ったり、真冬にストリートライブをやったりも。
作曲のコンペは採用されなければ収入がゼロ。当時は1~2曲くらいしか採用されなかったと記憶しています。周りからは、音楽活動を続けられるのかと心配されましたが、当時の僕はそれほど切羽詰まってはいませんでした。黙々と、曲を作っていましたね。
ソロになってからすぐに、音楽だけで食べていけるものなのでしょうか?
一年ほど、音楽の傍ら派遣で事務の仕事をしていました。職務経歴書の添削をしてましたね。
それまで、アルバイトといえば引越しスタッフとか清掃とか、タウンページ配りとかしかやったことがなかったので、東京のオフィスで働くって「なんて快適なんだ」ってびっくりしました。「ナニコレ!天国!!」って。暑くもなく寒くもなく、いつでも好きな時にトイレいけるし、男性ばかりじゃないし、最高だなって思って(笑)
あはは。それを一年ほど?
そうですね。
ちょうどそういうときに吉井和哉さんのツアーにコーラスで参加できることが決まったんですよ。それからは、音楽一本で食べています。2009年のことなので、もう10年以上経ちますね。